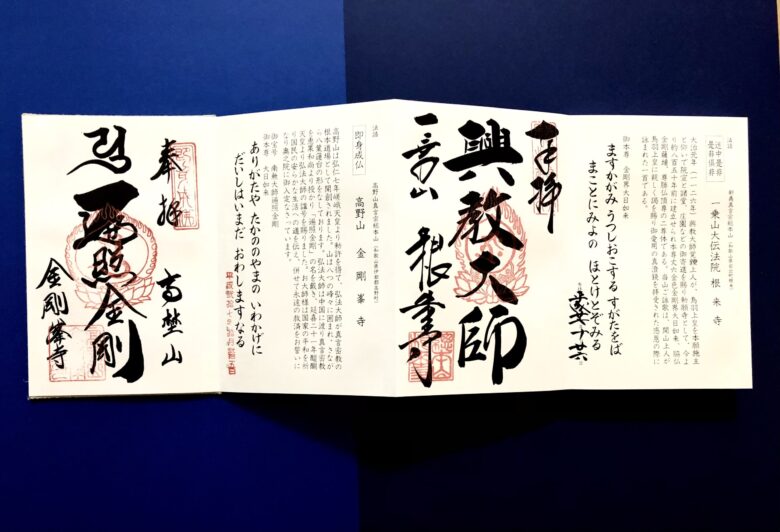こんにちは。
【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。
今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。
京都の白川南通と新橋通が交わる場所にあり、祇園町のシンボルとなっているのが「辰巳大明神(辰巳神社)」です。
今日は、辰巳大明神(辰巳神社)と祇園白川・祇園新橋周辺の見どころをご紹介します。
辰巳大明神(辰巳神社)

辰巳大明神は、祇園のほぼ中央に鎮座するとても小さな神社です。
もともとは南東の方角を守る神社で、京都御所の辰巳(南東)の方向を守る鎮守社として建立されました。
御祭神は、狸です。
御祭神が狸とは珍しいですが、これには逸話が残っていて、むかし辰巳大明神の横にある巽橋に狸が住んでいて、この橋を渡る人を騙し、川の中を渡らせるという悪戯をするので困った人々が、狸を祀る祠を建てると、狸の悪戯がピタリとおさまったのだそうです。
境内に狐の像が安置されてからは、辰巳稲荷(たつみいなり)とも呼ばれるようになり、「祇園のお稲荷さん」と親しまれています。
祇園で働く舞妓や芸妓の信仰を集めるようになり、今では諸芸上達や商売繁盛のご利益があると、芸事の上達を願う芸妓さん舞妓さんの姿がよく見られます。

辰巳大明神の周辺には、奉納された朱色の灯籠や玉垣などが並んでいます。
春には、神社をすっぽり覆うように桜が咲き、多くの人で賑わいます。
祇園白川・祇園新橋
辰巳大明神が鎮座する祇園白川(ぎおんしらかわ)と呼ばれる地域は、新橋通と白川に面する辺りをいい、祇園東の芸妓さん舞妓さんが通うお茶屋が立ち並んでいます。
その景観は、美しく、古さと情緒のある街並みとなっており、その街並みは、祇園新橋として伝統的建造物群保存地区に指定されています。

新橋通りを中心とした東西約160メートル、南北約100メートルの範囲が保存地区で、1865年の大火直後に建てられた建物で、切妻造の二階建てとなっています。二階が座敷で「すだれ」が掛かかり、茶屋町を感じさせます。
祇園は、八坂神社の門前町として四条通の南北に発展した花街です。
1732年に幕府から正式に茶屋営業の許可が下りてからは、元吉町、橋本町、林下町、末吉町、清本町、富永町の「祇園内六町」がつくられました。現在の祇園新橋は、この祇園内六町の内の本吉町です。
「祇園内六町」最盛期の江戸末期ごろには、祇園には500軒もの茶屋がありましたが、戦後、多くの茶屋がビルに建て替えられてしまい、祇園新橋は茶屋の町並みが残る貴重な場所となっています。
祇園北部の祇園新橋周辺は「伝統的建造物群保存地区」に指定されていますが、祇園南部の花見小路を挟む一帯は「歴史的景観保全修景地区」に指定されていて、こちらも京都の風情を楽しめる場所として人気の観光スポットとなっています。
花見小路は観光客のマナーが問題となり、現在残念ながら撮影禁止スポットとなっていますが、写真を撮れなくても、その美しい街並みは訪れる価値ありですので、是非散策してみて下さい。
辰巳大明神(辰巳神社)周辺の見どころ
辰巳大明神の周辺は、祇園の中でも特に風情ある場所として人気を集め、雑誌やテレビなどでこの周辺風景が使われ、ドラマや映画にも度々登場しています。

辰巳大明神のすぐそばにある巽橋です。
白川にかかる切通しという路地へと続く小さい橋です。
巽橋では、毎年6月第1日曜日に、生き物を自然に放すことにより功徳を積むという仏教由来の放生会(ほうじょうえ)が行われます。
鮎・鯉・金魚などの稚魚2千匹ほどが、舞妓さん芸妓さんの手によって放流され、香煎茶がふるまわれる行事で、一般の方も指定の場所から見学可能となっています。

白川沿いにも、情緒あふれる建物が立ち並び、写真スポットとしてもおすすめです。

祇園を愛した吉井勇の歌碑も建っています。
「かにかくに祇園はこひしぬるときも枕の下を水のながるる」
四条通には、南座があります。
南座は、江戸時代初期、元和年間に官許されたとされる劇場で、同じ場所で興行を続けてきたという意味では、日本最古の劇場となっています。
アクセス
住所:京都市東山区新橋花見小路西入ル元吉町
京阪電車:「祇園四条駅」下車 9番出口から徒歩4分
阪急電車:「河原町駅」下車 1A・1Bで口から徒歩8分
いかがでしょうか?
祇園は、古くから伝わる京都の花街で、その風情ある雰囲気に魅了されること間違いなしです。
散策だけではなく、買い物やグルメも楽しむことができる祇園で、京都を堪能してみてはいかがでしょうか?
それでは、また。