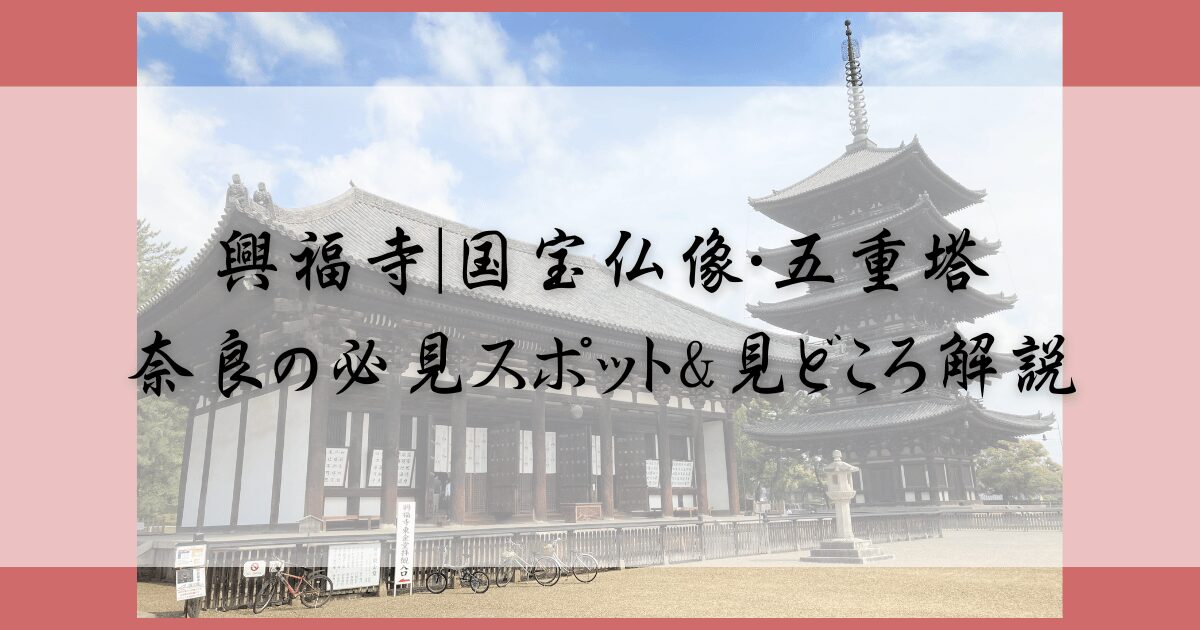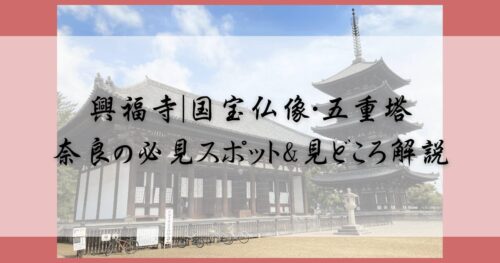奈良駅から徒歩5分、春日大社や東大寺にも歩いてすぐの場所にある「興福寺」。
国宝や重要文化財を数多く所蔵し、美しい伽藍が立ち並ぶ興福寺は、奈良観光には欠かせないスポットです。この記事では、興福寺の歴史や見どころを詳しくご紹介します。
興福寺とは?
興福寺と言えば、奈良のシンボルとも言える「五重塔」や、仏像ファンの間で圧倒的な人気を誇る「阿修羅像」が有名です。
また、境内には多くの堂宇があり、各所で美しい仏像や建築を楽しめます。
興福寺の歴史
興福寺の歴史は、藤原鎌足の妻である鏡大王が山階寺を創建したことに始まります。
710年の平城遷都に伴い、藤原不比等が厩坂寺を現在の地に移し、「興福寺」と改名しました。奈良時代には「四大寺」の一つとして数えられ、多くの堂塔が建立されました。特に五重塔や東金堂は有名です。
平安時代に入ると、興福寺は春日社(現在の春日大社)の実権を掌握し、大和国を支配するほどの勢力を持つようになりました。藤原氏の氏寺として発展し、多くの政治的影響力を持ちました。
1180年、平重衡による南都焼討ちで伽藍の大半が焼失しました。しかし、僧信円らの尽力で復興が進みました。
1717年には火災で伽藍の西半分を失いました。この後、中金堂は仮堂として再建されました。文禄4年(1595年)の検地では「春日社興福寺」として2万1千余石の知行が認められ、徳川政権下でもその地位が保たれました。
1868年の神仏分離令により、興福寺は大きな打撃を受けました。五重塔が売却されそうになるなど荒廃しましたが、僧侶や支援者たちの努力で復興が進みました。しかし、1881年に再興許可が下り、伽藍再建が再開されました。
また、2018年に中金堂が約300年ぶりに再建され、創建当時の様式を可能な限り再現する形で復元されました
興福寺はその長い歴史を通じて、度重なる災害や変遷を経ながらも、日本文化と歴史において重要な役割を果たしてきました。
興福寺の見どころ
興福寺には、見どころがたくさんあります。
国宝や重要文化財に指定された建造物や仏像が多く、境内を歩くだけでも歴史の重みを感じられる場所です。
ここでは、興福寺の代表的な見どころを紹介していきます。
五重塔

こちらは興福寺の五重塔です。
現存の五重塔は1426年頃に再建されたもので、高さは50.1メートルです。
木造の塔としては、京都・東寺の五重塔に次いで日本で2番目に高い塔です。※東寺の五重塔と桜のライトアップの様子はこちらの記事で詳しくご紹介しているので、美しい様子をぜひチェックしてみてください。
現在、五重塔は120年ぶりとなる大規模な保存修理工事中で、工事は2023年7月5日から2031年3月まで続く予定です。
工事期間中は、工事用の覆屋で覆われているため、残念ながら五重塔の姿を見ることができません。
三重塔
興福寺と言えば、五重塔を思い浮かべますが、実は三重塔もあります。
三重塔は国宝に指定されて、北円堂と並んで、興福寺内で最も古い建築物の一つとされています。
現存する三重塔は鎌倉時代前期(1185〜1274年)に建てられたものと考えられています。その高さは約19メートルです。
毎年7月7日に「弁財天供」が行われ、この日には内部を拝観することができます。
南円堂

南円堂は八角形の優美な建物で、重要文化財に指定されています。
毎年10月17日に「南円堂特別開扉」が行われ、通常は非公開の堂内を参拝することができます。この日には、ご本尊である国宝の木造不空羂索観音菩薩坐像が公開されます。
南円堂は、西国三十三所観音霊場の第九番札所で、いつも巡礼者で賑わっています。

813年(弘仁4年)に藤原冬嗣が父・内麻呂の冥福を祈って創建しました。
現在の建物は1789年(寛政元年)に再建されたもので、4度目の建替えとなります。
堂内には、ご本尊の不空羂索観音像のほか、四天王立像、法相六祖坐像が安置されており、これらはすべて国宝に指定されています。
東金堂

五重塔と並んで建っているのが東金堂です。
現在の建物は、応永22(1415)年に再建されたものです。最初の建立は726年、聖武天皇が母・藤原宮子の病気平癒を祈願して建てられました。
興福寺の主要な堂宇の一つで、国宝に指定されています。

堂内には、ご本尊である薬師如来坐像を中心に、日光・月光菩薩立像、文殊菩薩坐像、維摩居士坐像、十二神将立像、四天王立像などが安置されています。
中金堂

現在の中金堂は2018年に再建されたもので、創建当初の様式を復元する形で行われています。
内部には、鎌倉時代に運慶周辺の仏師によって制作された力強く躍動感ある像で、以前は南円堂に安置されていた国宝の四天王立像と、重要文化財の吉祥天倚像が安置されています。
中金堂は興福寺の中心的な建物であり、創建当初から伽藍の核として機能してきました。再建後も、その威容と内部に安置された貴重な仏像が多くの参拝者を引き付けています。
興福寺の中金堂は内部が非公開のため、内部に入ることはできませんが、中金堂の再建は外観の復元に重点が置かれましたので、外からだけでも十分に見る価値があります。
国宝館
興福寺の見どころのハイライトとも言えるのが「国宝館」。ここには、仏像ファンならずとも一度は見てみたい阿修羅像が安置されています。
阿修羅像は、八部衆の一尊で、像高153.4cm、繊細な顔立ちと6本の腕が特徴的。仏像鑑賞の醍醐味を存分に味わえます。
国宝館には他にも天燈鬼・龍燈鬼立像(国宝、鎌倉時代)や板彫十二神将立像(国宝、平安時代)など、注目すべき仏像が安置されています。
興福寺は日本で最も多くの国宝仏像を所有しています。中でも「彫刻」カテゴリーの国宝136件のうち、興福寺所有は18件で、全国1位です。
興福寺の国宝館は、まさに「国宝仏像の宝庫」呼ぶにふさわしい場所です。阿修羅像をはじめとする多くの貴重な仏像を一度に鑑賞できる、仏像ファンにとって非常に魅力的な場所です。
<国宝館の拝観情報>
拝観時間:9:00〜17:00(受付終了は16:45まで)
拝観料:大人700円
興福寺 基本情報・アクセス
JR,近鉄どちらからも、奈良の鹿に癒されながら、のんびり歩いていると、すぐにたどり着きますよ。

ツアー検索はこちら⇒クラブツーリズムで興福寺を巡るツアーをチェック✅
※プロモーションを含みます