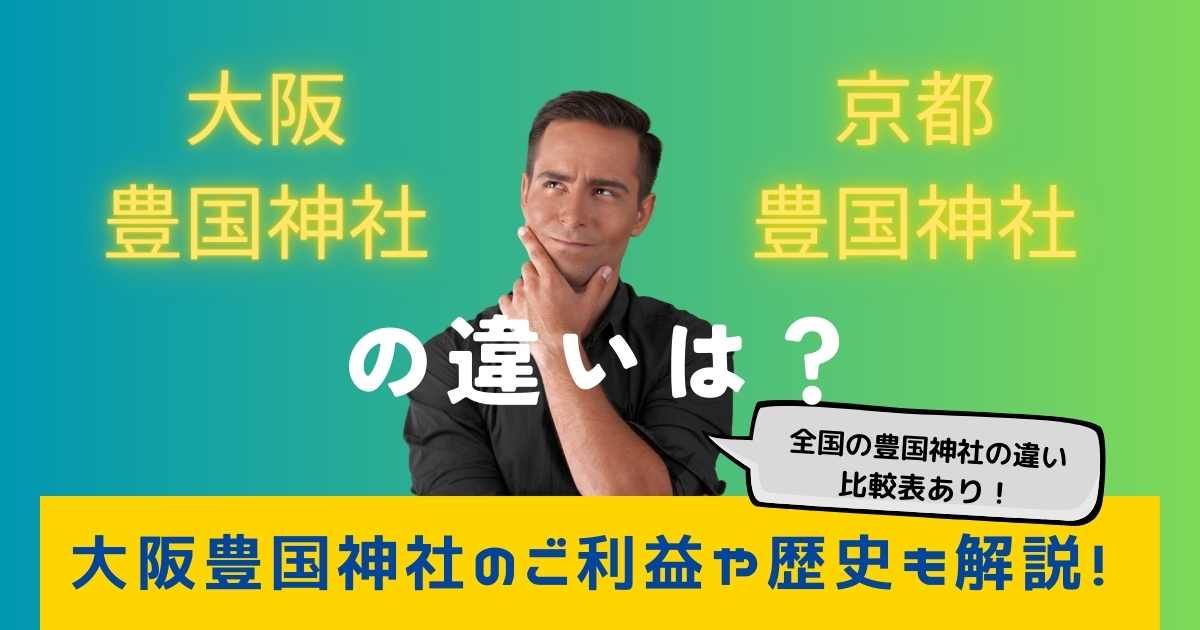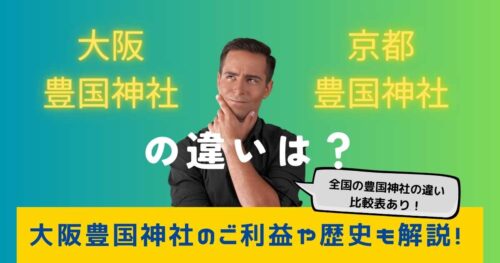大阪城公園内にある「豊国神社」は、豊臣秀吉・秀頼・秀長を祀る出世開運の神社。この記事では京都の豊国神社との違いや、全国の読み方・御祭神の違いも一覧で解説します。
もちろん、大阪城公園内にある豊国神社の歴史やご利益、大阪城観光などもしっかりと解説しますよ!
「大阪観光で立ち寄れるパワースポットを知りたい」「豊臣秀吉ゆかりの神社について知りたい」そんな方はぜひご覧ください。
大阪城公園にある「豊国神社」とは?
大阪城と言えば、豊臣秀吉が築いた城として知られています。その大阪城公園内、二の丸南側にあるのが豊国神社です。
この神社には、
- 豊臣秀吉(主祭神)
- 豊臣秀頼(秀吉の子)
- 豊臣秀長(秀吉の弟)
の三柱が祀られています。
境内には秀吉像があり、訪れる人々はその堂々たる姿に圧倒されつつも、出世運や成功運の上昇を願って参拝します。
大阪城・豊国神社の歴史

豊臣秀吉が亡くなったのは慶長3年(1598年)。
その功績を称え、朝廷から「豊国大明神(とよくにだいみょうじん)」の神号を賜り、京都東山など各地に豊国神社(当時は豊国社)が創建されました。
しかし、豊臣家が滅亡すると徳川家康の命によってその神号は廃され、神社も姿を消してしまいます。
時を経て、明治時代に明治天皇が大阪を行幸された際に再興が命じられ、明治12年(1879年)、京都の豊国神社の分社として創建されました。
その後、大正10年(1921年)に京都から独立し「豊国神社」となりました。
創建当時は現在の大阪市中央公会堂付近にあり、大正時代には大阪市役所周辺へ移転。そして昭和36年(1961年)に、現在の大阪城公園内へと遷座されました。
京都と大阪の豊国神社、2つの違いとは?

京都と大阪にある豊国神社ですが、実は大きな違いが2つあります。
2つの違いを詳しく見ていきましょう。
違い1:読み方が違う
まず最も大きな違いは、名前の読み方です。
- 京都の豊国神社 → とよくにじんじゃ
- 大阪の豊国神社 → ほうこくじんじゃ
同じ漢字ですが、地域によって読み方が異なるのは珍しいですよね。
この読みの違いには、祀られている神様の構成が関係しているともいわれています。
それでは、もう一つの違い、主祭神についても詳しく解説していきます。
違い2:祀られている神様が違う

京都の豊国神社は、豊臣秀吉ただ一柱を祀っているのに対し、大阪の豊国神社は秀吉に加え、秀頼と秀長の三柱をお祀りしています。
この違いが、神社としての成り立ちや性格にもわずかながら影響を与えていると考えられます。
また、社殿や境内の雰囲気、秀吉像の表情やポーズも異なり、参拝すると「同じ名前なのにまったく違う神社」と感じられるでしょう。
👉 【京都】豊臣秀吉が祀られたパワースポット「豊国神社」徹底ガイド
京都の豊国神社は、社殿も秀吉像も派手ですよ!ぜひ比較してみてください。
全国の豊国神社と読み方の違い
京都と大阪の豊国神社の違いを解説してきましたが、全国には「豊国神社」と名のつく神社が数多く存在し、そのすべてが同じではありません。
祀られている神様や、神社の成り立ち、名前の読み方などに違いがあるのです。
ここでは、主要な豊国神社を「読み方」「所在地」「創建年」「御祭神」「特徴」の5項目でまとめてご紹介します。
旅行先で見かけた豊国神社がどんな由来を持っているのか、ぜひチェックしてみてください。
| 読み方 | 所在地 | 創建年 | 御祭神 | 特徴・由来 |
|---|---|---|---|---|
| とよくにじんじゃ | 京都府京都市東山区 | 1599年 | 豊臣秀吉 | 秀吉公没後に創建された本社 |
| とよくにじんじゃ | 石川県金沢市東御影町 | 1616年 | 豊臣秀吉 | 加賀藩前田家が密かに祀っていた社 |
| とよくにじんじゃ | 岐阜県大垣市墨俣町 | 1992年 | 豊臣秀吉 | 一夜城(墨俣城)に由来。白鬚神社の内社 |
| とよくにじんじゃ | 愛知県名古屋市中村区 | 1885年 | 豊臣秀吉 | 秀吉の生誕地・中村公園内 |
| とよくにじんじゃ | 京都府京都市東山区(新日吉神宮末社) | 不明 | 豊臣秀吉 | 樹下社(このもとのやしろ)として知られる |
| とよくにじんじゃ | 徳島県小松島市中郷町 | 1614年 | 豊臣秀吉 | 地元に伝わる秀吉伝承に基づいて創建 |
| ほうこくじんじゃ | 滋賀県長浜市南呉服町 | 1600年 | 豊臣秀吉、事代主大神、加藤清正、木村重成 | 長浜城主時代の秀吉に由来。加藤清正らも祀られる |
| ほうこくじんじゃ | 大阪府大阪市中央区大阪城 | 1879年 | 豊臣秀吉、豊臣秀頼、豊臣秀長 | 秀吉・秀頼・秀長の三柱を祀る |
| とよくにじんじゃ | 広島県廿日市市宮島町(千畳閣) | 1587年頃 | 豊臣秀吉(※明治以降に神社として祀られる) | 秀吉が建立を命じた大経堂 → 神仏分離で神社化 |
| ほうこくじんじゃ | 福岡県福岡市博多区奈良屋町 | 1886年 | 豊臣秀吉 | 博多の豪商が建てた祠が起源 |
表をご覧いただくとわかるように、豊臣秀吉のみを御祭神として祀る神社は「とよくにじんじゃ」と読むケースが多く、
一方で、大阪や長浜など複数の人物を祀っていたり、武将を中心とした構成の神社は「ほうこくじんじゃ」と呼ばれている傾向があります。
読み方と祀られている神様の関係性を知ることで、それぞれの神社の個性がより鮮明に見えてきますね。
大阪の豊国神社のご利益は?
主祭神の豊臣秀吉は、農民から天下人にまで成り上がった人物。そのため大阪の豊国神社では、
- 出世運
- 成功運
- 商売繁盛
- 勝負運
といったご利益があるとされています。
ビジネスマンや受験生にも人気のパワースポットです。
豊国神社から大阪城観光へ|所要時間と楽しみ方

豊国神社そのものは比較的小規模な神社なので、参拝には20分もかからないでしょう。
ただし場所は大阪城の南側。
参拝後はぜひ天守閣や庭園、さらに周辺施設「ミライザ大阪城」にも足を延ばしてみてください。
ミライザ大阪城は、1931年築の陸軍司令部庁舎をリノベーションした施設で、レストランやカフェ、お土産店などが充実。城の風情とモダンさが融合した空間です。

大阪城のお堀を巡る「御座船(ござぶね)」は、お堀の秘密などの解説付きで歴史も学べておススメです。御座船の詳細については、こちらのページでご確認ください。
観光・参拝・食事を組み合わせて、半日ゆったり楽しむプランがおすすめです。大阪城公園をゆっくり散策するのも気持ちいいですよ!
【大阪城 豊国神社】アクセス基本情報
大阪と京都、どちらの豊国神社にも豊臣秀吉の歴史が色濃く息づいています。
出世運や開運を願って、2つの神社を巡る“豊臣ゆかりのパワースポット旅”もおすすめです。
大阪城を訪れた際は、ぜひ豊国神社にも立ち寄ってみてください。