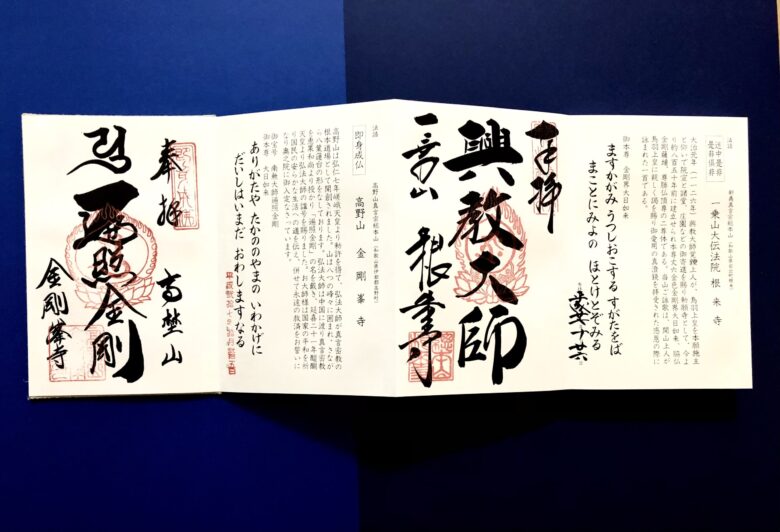こんにちは。
【夫婦でお参り】のHOKI & MIYUです。
今日もポチポチと、神社仏閣に関わる情報をお届けします。
聖徳太子ゆかりの地、斑鳩の里に三重塔で知られている法起寺という寺があります。
秋にはコスモスの花が楽しめるスポットとしても人気です。
今日は、平成5年に法隆寺とともに世界文化遺産に登録されている「法起寺」をご紹介します。
法起寺(ほうきじ・ほっきじ)
法起寺は、「ほうきじ」「ほっきじ」という読み方があります。
法隆寺地域の仏教建造物のひとつとして世界遺産の登録には、「ほうきじ」を正式名称としています。
法起寺は、法隆寺、中宮寺などと共に「太子御建立七ヵ寺」に数えられ、国内最古級の寺院のひとつです。それでは、その歴史を詳しく見ていきましょう。
法起寺の歴史
法起寺は、622年に聖徳太子が法華経を講じたという岡本宮(おかもとのみや)を、聖徳太子の子である山背大兄王(やましろのおおえのおう)に、寺に改めるよう遺言し、寺として改めたられたのが始まりと伝わっています。
その後、638年に福亮僧正が、聖徳太子のために弥勒像一躯と金堂を造立します。そして685年には、恵施僧正が宝塔の建立を発願し、706年に塔の露盤を造ったとされています。
天平時代の記録には、池後尼寺(いけじりにでら)と記されていることから、当初尼寺として建立されたと言われています。
ちなみに、法起寺は、岡本の地に存在していることから岡本寺とも呼ばれ、他にも池後寺・岡本尼寺とも呼ばれていました。
現存する最古の三重塔

国宝に指定されている法起寺の三重塔の高は24m、飛鳥時代、706年に建立された塔で、国内に現存する三重塔の中では最古のものです。
勾配の緩やかな屋根といった特徴は、法隆寺の五重塔と同じ、法隆寺系建築様式の建造物となっています。
また、初重内部は土間で、四天柱と八角の心柱を立て、四天柱の基本構造は斗(ます)と呼ばれる部品と、肘木(ひじき)と呼ばれる部品を組み込まれており、飛鳥時代の建築様式を見ることができます。
ご本尊:十一面観音像

ご本尊である十一面観音像は、重要文化財に登録されています。
平安時代製作されている木造の像高3.5mの像で、現在は収納庫に安置されています。
十一面観音像というと、一般的に女性らしい美しい身体つきの像が多いですが、法起寺の十一面観音像は、肩幅ががっしりとした男性的身体つきをしています。
この特徴は、奈良時代の十一面観音像には多く見られますが、平安時代に製作された仏像としては大変貴重と考えられます。
写真撮影できませんので、ご本尊のお姿は法起寺公式ページで少しだけ拝見することができます。ご覧いただくと、肩がかっしりとしている様子もお分かりいただけます。
その他の境内の建造物の様子です。

こちらは、講堂、江戸時代の建造物です。

聖天堂、こちらも江戸時代の建造物です。

池から見る三重塔も趣を感じます。
秋には三重塔を背にコスモス畑が広がる

法起寺は、秋にはコスモス寺としても人気のスポットとなっています。
可愛らしいコスモスと日本最古の三重塔のコラボレーションを見ようと、多くの人が訪れます。
コスモス寺として人気の法起寺ではありますが、コスモスは境内に咲くわけではありません。法起寺の周りにはのどかな田園風景が広がっていて、秋には法起寺の周りがコスモス畑になります。
コスモスの開花時期は、例年10月上旬から10月中旬となっています。
日本最古の三重塔を背に天を仰ぐコスモス群の美しい写真が撮影できますよ。
【法起寺】アクセス基本情報
【法起寺】基本情報
住所:奈良県生駒郡斑鳩町岡本1873
電話:0745755559
参拝:8:30~16:30
HP:http://www.horyuji.or.jp/hokiji/
アクセス:JR法隆寺駅より徒歩約35分
JR法隆寺駅よりバス「法隆寺参道」行き法隆寺参道下車
JR王寺駅よりバス「国道横田・シャープ前・法隆寺前」行き法隆寺前下車
近鉄電車筒井駅よりバス「JR王寺駅」行き法隆寺前下車
電車では、JR法隆寺駅から2.5kmのため、バスに乗り換え「法起寺前」下車徒歩すぐです。
法輪寺とは、歩いて10分程度です。法隆寺~中宮寺~斑鳩神社~法輪寺~法起寺のルートを辿ると、スムーズに散策ができます。
斑鳩の里で、のどかな田園風景を楽しみながら、飛鳥時代の歴史的建造物を巡るのもなかなかのものですよ。
それでは、また。