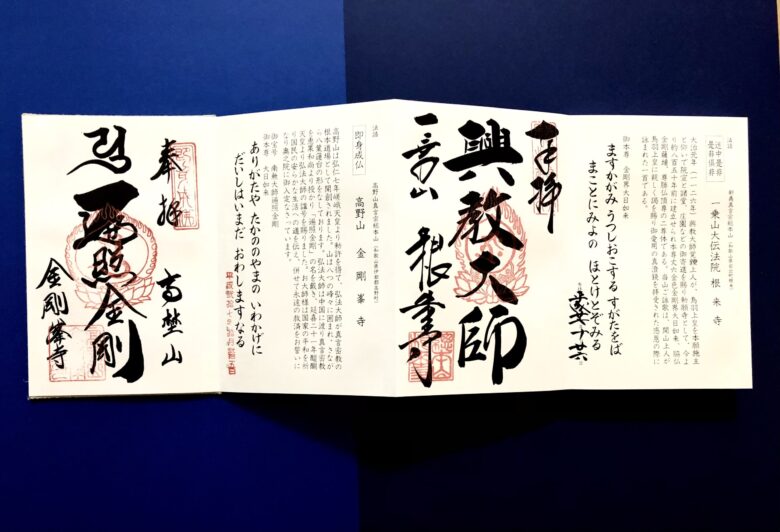福岡市博多区の「櫛田(くしだ)神社」、お櫛田さんと呼ばれ親しまれている博多の総鎮守です。
7月の博多祇園山笠や10月の博多おくんちなど、多くのお祭りで賑わう神社です。
そんな櫛田神社の節分大祭は、巨大な大お多福面の設置や豆まきなどが催され、多くの参拝者で賑わいます。
今回は、櫛田神社の節分大祭をご紹介します。
日本一大きな大お多福面は「いつから、なぜ設置されるようになったのか?」その由来についてもご紹介します!
日本一巨大な「大お多福面」

櫛田神社で行われる節分大祭は、鳥居に設置される巨大な大お多福面が有名です。
2月3日の節分を前に毎年「大お多福面」が設置されます。(2023年の設置は1月15日~2月15日)

この巨大な大お多福は、櫛田神社の楼門、南神門、北神門の3つの門に設置されます。
一番大きいお多福面は、正面の楼門に取り付けられているもので、高さ5・3メートル、幅5メートルの大きさがあります。
お多福面は、上中下の3つのパーツに分けることができるそうで、分けて保存してパーツを氏子さんたちが、毎年組みたてるのだそうです。
お多福面の空いた口をくぐると、商売繁盛や家内安全などの福を授かることができると言われています。
巨大「お多福面」いつから、なぜ設置されるようになった?
櫛田神社の創建は757年ですが、お多福面の設置が始まったのは1961年です。
お多福面設置のきっかけは、一人のサラリーマンでした。
それが、田中諭吉氏です。
当時、広告代理店で働いていた田中諭吉氏が、1961年の節分大祭の時に巨大お多福を思いつき、始まったと言われています。
田中諭吉氏は、ユーモアで斬新な企画を出すことで有名だったそうで「博多のアイデアマン」と呼ばれていたそうです。
巨大お多福と言うだけでもインパクトがある上に、お多福の口に自分から飛び込むという面白さ、確かにユーモアと斬新さがありますね。
その思い付きが、60年以上も引き継がれる恒例行事になっているなんて凄いです!
櫛田神社「節分大祭」

櫛田神社の節分大祭は、江戸時代末期から盛大に行われてきた年中行事で、毎年立春の前日に開催されます。
日本一の大お多福面や超特大の福枡が飾られ、多くの参拝者で賑わいます。
2月2日に大お多福の清祓いとくぐり初め、2月3日は節分大祭の豆まき神事が行われます。
「豆まき」や「宝まき」が行われる能舞台の周りは、福を授かろうとする参拝者で埋めつくされます。
豆まきには、毎年有名なゲストも多数参加されることでも知られています。
2023年は、3年ぶりに豆まき神事が通常開催され、有名歌舞伎役者さんらが参加する予定となっていますよ!
| 開催場所 | 櫛田神社:福岡県福岡市博多区上川端町1−41 |
| 開催日時 | 2023年2月3日 豆まき/10:00~16:00 ※状況により変更となる場合あります |
| 電話 | 092-291-2951 |
| アクセス | 地下鉄「祇園駅」から徒歩約5分 |
節分大祭の終わりには、縁起物も忘れずにチェック!
福をかき寄せ商売繁盛を願う熊手「福寄せ」や、ひしゃくで福をすくい取る「福寿久井(ふくすくい)」、福が増すよう願う「福桝(ふくます)」など、6種類の縁起物も用意されています。
おたふく面が取り付けられていて見た目も可愛い縁起物ですよ!