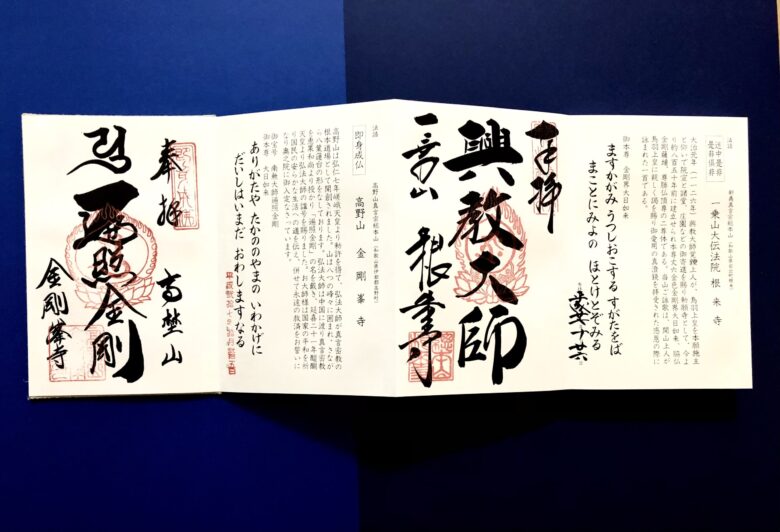京都市北区にある「正伝寺(しょうでんじ)」は、狩野山楽による襖絵や美しい枯山水庭園が有名なお寺です。
その静かで美しい庭とは相反する、生々しさの残る伏見城の遺構「血天井」も見ることができます。
今回は、京都市北区の正伝寺をご紹介します。
京都の観光スポットが集まる地域からは離れているため、訪れる人は多くなく、静寂の中でゆっくりとお庭を楽しめるオススメの場所ですよ!
正伝寺(しょうでんじ)

正伝寺は、正式名称を吉祥山正伝護国禅寺という臨済宗南禅寺派の寺院です。
1268年、東巌慧安の師である兀庵普寧を開山とし、烏丸今出川に創建したのが始まりといわれています。
寺は比叡山延暦寺の衆徒によって破却され、その後、1282年に現在の地に再建されました。
室町時代には、天皇家や将軍家の帰依を受けましたが、応仁の乱により衰退し、後に豊臣秀吉や徳川家康の援助を受け復興しました。
江戸時代には、塔頭5寺を有していたといいます。
正伝寺の見どころ

山門を抜けると本堂まで、250mほどの坂道を登ります。
周りは緑に囲まれ、新緑の季節はとても気持ちが良いです。

坂の途中に鐘楼が建っています。

登り切った場所に庫裏(くり)が建っています。
庫裏の左に拝観受付があります。
正伝寺の方丈(本堂)は、1653年に南禅寺の塔頭「金地院」の小方丈を移建したもので、桁行13.8m、梁間10m、一重、屋根は入母屋造、こけら葺の方丈となっています。
障壁画は狩野山楽一派の筆とされています。
※正伝寺は、方丈から庭園の撮影はOKですが、内部の撮影はできません。
獅子の児渡し庭園

このお寺の一番の見どころは、本堂の前の美しい枯山水の日本庭園です。
この庭は「獅子の児渡しの庭園」と呼ばれています。
白砂が敷き詰められ、さつきが植えられています。
通常、枯山水庭園と言えば「岩」を使って「島」を表現するのですが、正伝寺のお庭は岩ではなく「さつき」で「島」を表現しています。
このさつきの木は、右から順に「七つ・五つ・三つ」の順に並んでいて、奇数は縁起の良い数字で「七五三式の庭」となっています。

奥にある門は、柿葺きの勅使門です。

遠くに望む比叡山を借景にしています。
市街地から離れてポツンと佇み、静寂に包まれたお庭で、思う存分、比叡山を借景とする枯山水のお庭を眺めることができるお寺です。
伏見桃山城の御成殿の遺構「血天井」
方丈の広縁の天井は、伏見桃山城の御成殿の遺構と言われています。
関ヶ原の戦いの直前に、伏見城に立籠った徳川方の重鎮鳥居彦エ門元忠をはじめ、三百八十余名が割腹し果てた廊下の板を天井としたもと伝えられています。
方丈の広縁の天井が血天井になっているので、知らずに行った方は、
他に誰もいない広縁に腰を下ろして、思う存分お庭を眺め、気持ちよく広縁に『ごろ~ん』と寝っ転がって天井を見上げたりしたら、衝撃が走るかもしれません。
その美しい景色とは裏腹に、天井には明らかに「血」の色をした人の手形が残っていて、複雑な気持ちになります。
血を見るのは苦手と言う方は、決して見上げないように。
【正伝寺】アクセス基本情報
【正伝寺】基本情報
住所:京都市北区西賀茂北鎮守庵町72
電話:075-491-3259
拝観時間:9:00~17:00
拝観料:400円
HP:http://shodenji-kyoto.jp/
アクセス:京都駅から西賀茂車庫行 9系統「神光院前」下車 徒歩約15分
静寂の中でゆっくりとお庭を楽しめるオススメの場所ですが、アクセスはちょっと不便です。
だからこそ、静寂を楽しめるのですが。
今回は、京阪電車の出町柳駅前のレンタサイクルを利用して参拝しました。
レンタサイクルを利用すると、北区の神社仏閣を巡れるので便利ですよ!