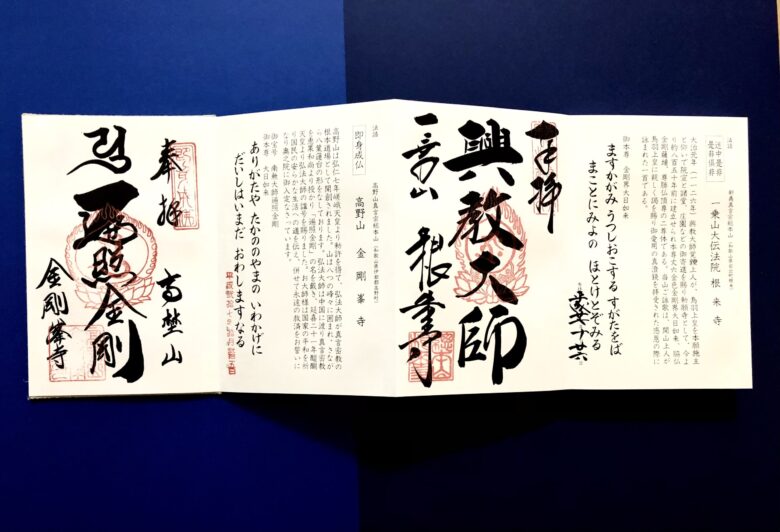大阪の地元で「すみよっさん」の愛称で親しまれている住吉大社は、全国に約2200社ある住吉神社の総本社です。
今回は、大阪市住吉区に鎮座する住吉大社をご紹介します。
住吉大社とは

住吉大社は、仁徳天皇の住吉津の開港以来、遣隋使・遣唐使などの航海の守護神として崇敬を集めました。
住吉大社のご祭神は、「底筒男命(そこつつのおのみこと)」 、「中筒男命(なかつつのおのみこと)」 、「表筒男命 (うわつつのおのみこと) 」です。
この底筒男命 、中筒男命 、表筒男命は、「住吉三神」と 呼ばれ、全国の住吉大社に祀られています。
日本書紀・古事記に記されている「伊邪那岐命(いざなぎのみこと)」が、火神の出産で亡くなった妻の「伊邪那美命(いざなみのみこと)」を連れて戻ろうと、黄泉の国に追って行った際にケガレを受け、そのケガレを清めるために海に入って禊祓したときに生まれたと言われています。
住吉大社には、海の神「住吉大神」をはじめ、商売発達の「はったつさん」など、たくさんの神様が祀られています。
厄除や身体健全、商売繁昌、家内安全、安産、交通安全など様々な御利益があると言われていますので、願い事を祈願してみてはいかがでしょうか。
住吉大社の境内見どころ
約3万坪の広さがある住吉大社の境内には、本殿4棟、摂末社あわせて27社、その他にも多くの見どころがあります。
渡るだけでお払いになる「反橋」

まずは、美しい橋「反橋(そりはし)」を渡ります。
神池にかかる神橋「反橋」は、「太鼓橋」とも呼ばれ、住吉大社を象徴する橋です。

反橋は、長さ約20m、高さ約3.6m、幅約5.5mで、最大傾斜が約48度もあります。
傾斜はきついですが、反橋を渡るだけで『お祓い』になると言われていますので、是非反橋を渡って本殿へ参拝しましょう。
神社建築史上最古の様式の一つ「本殿」

現在の本殿は、文化7(1810)年に建てられたものです。

神社建築史上最古の様式の一つと言われ、国宝建造物に指定されています。

第一本宮から第四本宮の4棟からなる「住吉造」となっています。
第一本宮から第三本宮までは直線状に並び、第四本宮と第三本宮が並列に配置されている、珍しい建築配置となっています。
屋根は、檜皮葺 (ひわだぶき) で、直線的な切妻造りが見事です。

屋根の檜皮葺と柱の朱色、壁の白、そこにさりげない金金具の装飾が美しく映えます。
青空とのコントラストも鮮やかで見事なのですが、この日は天気が良く逆光のため写真では伝わりにくいのが残念です。
住吉大社の広大な敷地には、見どころがたくさんあります。
ゆっくりと散策しながら巡ってください。
住吉大社アクセス
住所:大阪府大阪市住吉区住吉2-9-89
HP:http://www.sumiyoshitaisha.net/
最寄り駅は、阪堺電車「住吉鳥居前駅」で下車すぐ、南海本線「住吉大社駅」からも徒歩約1分ほど
今回は、全国に2,300社余りある住吉神社の総本社、大阪市住吉区の住吉大社をお届けしました。
ところで、
この「住吉(すみよし)」という地名、日本全国でよくみられる名前なのですよね。
住吉三神を祀る「住吉神社」があることに因んで地名がつけられているところが、多いそうですよ。