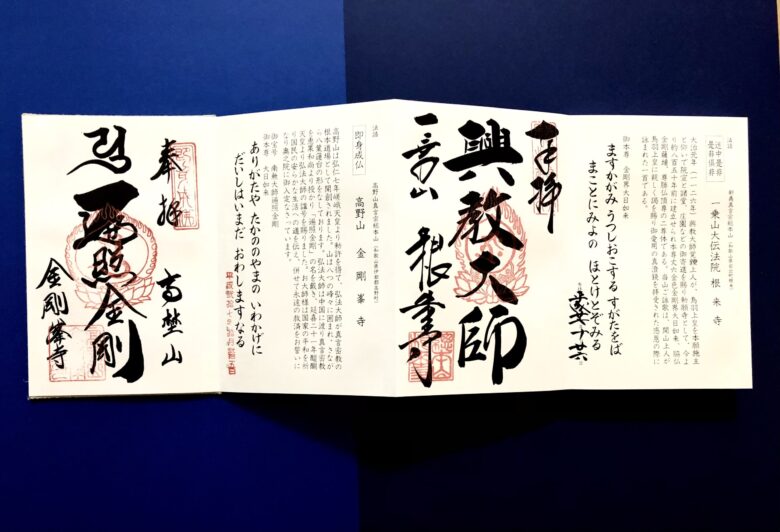風水思想に基づいて建てられた個性的な門「牌楼(ぱいろう)」で囲まれている横浜中華街には、関羽様を商売繁盛の神様として祀った「関帝廟(かんていびょう)」と、あらゆる神様を祀った「媽祖廟(まそびょう)」の2つのパワースポットがあります。
参拝方法は、中国式で日本に居ながら、ちょっと珍しい体験もできるので、横浜中華街に行くならグルメ食べ歩きだけじゃなく、「関帝廟(かんていびょう)」と「媽祖廟(まそびょう)」も、是非参拝して欲しいスポットです。
今回は、「横濱媽祖廟(よこはま まそびょう)」のご利益や、参拝方法、媽祖様についても詳しくご紹介します。
「関帝廟」については、下の記事でご紹介していますので、合わせて読んでみて下さいね!
目次
橫濱媽祖廟(よこはま まそびょう)
横濱媽祖廟は、横浜中華街にある廟で、御神体として海の守り神・天上聖母「媽祖(まそ)」が祀られておいます。
正式名称は、横浜大天后宮といいます。
現在の媽祖廟は、明治時代に置かれた清国領事館の跡地にあります。
横濱媽祖廟ができたのは2006年ですが、1400年代半ばから日本の媽祖崇拝が行われたと言われ、横浜以外にも日本各地に媽祖様が祀られている場所があります。
媽祖(まそ)さまとは
媽祖廟に祀られている「媽祖様」は、北宋時代、今から数千年も前の中国福建省の小さな漁村で生まれた「林黙娘(りんもうにゃん)」という実在した女性です。
誕生した時には、特別な存在であることを示してか、部屋中が赤い光と香りで包まれていたと言われています。
林黙娘さんは、小さい頃から才知に長けて、16歳のころに神から導かれ、特別な力を身につけ、各地で災難を退け人々の病を癒し、多くの人を助けました。そのため「通玄の霊女」と崇拝されるようになったと言われています。
そして、28歳の9月9日に修行を終えて天に召されます。
その後、赤い衣装をまとった林黙娘が、海上を舞って難民を救助する姿を見た人々は、廟を建てて護国救民の神様として祀るになったのです。
歴代の皇帝も「天妃」「天后」「天上聖母」などの称号を贈り敬意を表したと伝わっています。
「媽祖」は、現在でも中国大陸、台湾、華僑が住む世界各地で信仰され続けています。
媽祖祭(まそさい)
媽祖祭(まそさい)は、特に台湾で開催される媽祖祭が有名です。
100年以上の歴史を持つ台湾最大の宗教イベント、台湾の二大巡礼の1つで多くの人々が熱狂するお祭りです。
毎年、媽祖様の誕生日である旧暦の3月23日前後で行われます。
開催される日程は、毎年旧暦1月15日の夜に神意を伺って巡行の日取りが決まるため、直前まで正確な日程が決まらないのが特徴です。
台中市大甲区にある「大甲鎮欄宮」を出発して、彰化県、雲林県と南下し、最終目的地である嘉義県の新港にある媽祖廟「奉天宮」を目指し、そして戻ってきてスタート地点の代行鎮欄宮に戻ります。
その距離は何と!全長300kmを超えで、巡行は9日間続きます。
そして、この9日間、多くの参拝者たちが媽祖様の乗った神輿と一緒に移動すると言う、とてつもない壮大なお祭りです。
橫濱媽祖廟の媽祖祭
台湾で絶大な人気を誇る媽祖様のお祭りは、台湾のイメージが強いですが、ここ横浜中華街の媽祖廟でも毎年媽祖祭が開催されています。
横浜中華街では、毎年春分の日(3月21日前後)に媽祖祭が行われています。
当日は午前中に媽祖廟で新生児成長祈願の祈祷が行われ、神殿の外から見学可能となっています。
そして午後からは、神輿巡行パレードが行われます!
媽祖様の乗る神輿とともに、獅子舞、龍舞、中国舞踊が出演する華やかなパレードになっています。
パレードでは伝統行事「神輿くぐり」に、観客も飛び入りで参加できます。
屋台などもあり中華街全体がお祭りムード、横浜中華街の媽祖祭も賑わいますよ!
横濱媽祖廟のご利益と参拝方法

横濱媽祖廟は、横浜中華街の南門シルクロード通り元町寄りの場所にあります。
参拝した日は、人が多すぎて門前面の写真が撮れませんでしたが、豪華でキラキラの門をくぐると、真ん中には階段と廟が建っています。
階段を上がる手前右手に神社で言う授与所のような場所があり、お守りなどがあります。
ここに参拝するためのお線香のチケットが買える券売機があるので、購入(500円)して階段を登りましょう。

階段中央まで上がると、媽祖廟と書かれています。龍も豪華です。
ここから階段が左右に分かれていますが、右に進みます。

階段を登りきると、お寺の方がいらっしゃるので、声をかけてチケットを出して、線香と媽祖様のお札をいただきます。
日本の違って真ん中に木の棒がついていて、かなり大きいお線香です。
ちなみに、参拝の手順も丁寧に教えていただけ、点香台でお線香に火を付けるのもやってくださいました。
お線香に火が付いたら、参拝していきます。
参拝順とご利益
お線香は、全部で5本です。
本殿回路には、5つの香炉があり、それぞれの別の神様が祀られていています。
香炉には数字が書かれているので、数字の順番に参拝、お線香を一本ずつ供えていきます。
それでは、参拝の順とそれぞれの神様のご利益をご紹介していきましょう。
1:玉皇上帝(ぎょくこうじょうてい)|国泰平安

一番目の香炉は、本堂向きではなく、門側に向かって設置されています。
祀られている玉皇上帝(ぎょくこうじょうてい)は、「天公」ともいわれる天の神様で、国泰平安のご利益があると言われています。
民間信仰では、最高神とも言われ篤い信仰を集めている神様で、すべての人間の行為を推し量って運命を決定すると信じられています。
2:天上聖母(てんじょうせいぼ)|航海安全、疫病忌避、健康祈願

2番目から4番目の香炉は、本殿の前に3つ並んでいます。
写真で分かりにくいですが、右が2の香炉、左が3の香炉、そして中央が4の香炉です。
2の香炉の神様は、天上聖母(てんじょうせいぼ)です。
天上聖母とは、媽祖様のことで、一般的に「媽祖」と呼ばれることが多く、海の女神です。
中国道教の中では最も位の高い神様とされ、災難から安全を守る偉大な力を持つ女神であると信じられています。
ご利益は、航海安全や疫病忌避、健康祈願と言われています。
3:臨水婦人(りんすいふじん)・註生娘娘(ちゅうせいにゃんにゃん)|安産、子宝
3番目の香炉には、臨水夫人と註生娘娘が祀られています。
臨水夫人は、安産の神様です。
母親には、強さを与え困難を乗り越える手助けをし、子供には、成長を16歳まで見守ってくれるといわれています。
安産のご利益があるとされています。
註生娘娘は、子授けの神様です。
右手には筆、左手には記録簿を持っていて、すべての出生を執り、子供が欲しい女性の味方です。
子宝のご利益があるとされています。
4:文晶帝君(ぶんしょうていくん)・月下老人(げっかろうじん)|学問、縁結び
4番番目の香炉は、文晶帝君と、月下老人です。
文晶帝君のご利益は、学問です。
学問の神様である文晶帝君は、公正さと思いやりと、平和の象徴とされて、学力アップ、合格祈願や学術の成功を願う多くの人から信仰されています。
月下老人のご利益は、縁結びです。
月下老人は、縁結びの神様と言われ、恋愛のみならず、人間関係や仕事、商売などの良いご縁を結んでくださいます。
5:福徳正神(ふくとくせいしん)|金運、財産安全

土地公としても知られる福徳正神は、中国古代農耕から生まれた五穀豊穣・蓄財祈願の信仰にもとづく土地神様です。
そのご利益は、金運、財産安全とされ、今では商売繁盛や成功を願う人々や企業からの信仰を集めています。
本殿参拝
本殿回路の参拝が終わったら、スタッフの方に声をかけて本殿内にも参拝しましょう。
参拝方法は、下記の手順で行います。
- 御神体前の拝礼台に跪く
- 合掌して三礼
- 心の中で自分の名前・住所・生年月日を告げた後、願い事をする
- 最後に一礼
本殿内に入ると、拝礼台(足元に赤いクッションが置かれた台)があるので、そこに跪きます。
手順がわからなくても、前に書いてくれていますし、スタッフの方も丁寧に教えてくだるので、心配いりませんよ。
参拝が終わったら、外へ、階段は登った側と逆側の階段から降りましょう。

本堂から出て撮った写真です。
すぐ側に横浜大世界があります。
おみくじも引きたい方は、中国式のおみくじの引き方手順を下の記事でご紹介していますので、読んでみて下さいね。
【橫濱媽祖廟】アクセス基本情報
【橫濱媽祖廟】基本情報
住所:神奈川県横浜市中区山下町136
電話:0456810909
通常開廟時間:9:00~19:00 ※大晦日などは変更あり
HP:http://www.yokohama-masobyo.jp/
アクセス:みなとみらい線「元町中華街駅」 3出口中華街口より徒歩3分
JR 京浜東北・根岸線の石川町駅からは、中華街口より徒歩10分ぐらいです。